情報処理安全確保支援士に合格しました
私事で大変恐縮ですが情報処理安全確保支援士(RISS)に合格しました!といっても1年前の話です(汗)。この資格の合格は、私にとって大きな達成感を伴うものであり、長い道のりの集大成ともいえます。というのもこの資格の受験はこれで4回目となり、ようやく合格を勝ち取ることができました。この記事では、合格までの経緯や学習の工夫について振り返りたいと思います。
これまでの経歴と試験への挑戦
私はSE歴15年で、主にWebシステムのプログラマーとしての経験がまあ、そこそこ豊富です。業務ではデータベース設計やアプリケーション開発に関わることが多く、セキュリティやネットワークの分野にはあまり深く携わってきませんでした。しかし、情報セキュリティが今後ますます重要になることを考え、次のステップとして情報処理安全確保支援士の取得を目指しました。
過去には応用情報技術者試験やデータベーススペシャリスト試験に合格しています。これらの資格を通じて基礎的なIT知識は身につけていましたが、セキュリティの分野では初歩的な理解に留まっており、合格までには多くの課題がありました。そもそも仕事でセキュリティについてあまり深く考えるような機会がなかったというのも大きかったんですけどね。
受験を通じた学びと苦労
情報処理安全確保支援士試験は、情報セキュリティの基礎から応用まで幅広い知識が求められます。具体的には、暗号技術、ネットワークセキュリティ、脆弱性管理、法令・規格に関する知識などが試験範囲となります。これらの分野の多くは、私にとって新しい領域でした。SE歴が10年以上あるのに…
初めて受験した際、知識不足と準備不足を痛感しました。特に午後問題では、応用的な知識や実務経験が不足しているために対応できない問題が多かったです。その後、次のような工夫をしながら学習を進めました:
- 参考書の活用と基礎知識の習得 初期段階では、情報処理安全確保支援士試験専用の参考書を使い、基礎知識のインプットに集中しました。特に暗号技術や脅威分析に関する章は繰り返し読み込むことで理解を深めました。
- 過去問の徹底的な演習 過去問は合格に向けた最大の武器です。試験の形式や出題傾向をつかむために、過去10年分の問題を解き、間違えた箇所を重点的に復習しました。これにより、問題の解き方や重要ポイントが徐々に見えてきました。
- 実務経験との結びつけ 実際の業務で活用できるセキュリティ知識を意識的に学びました。例えば、脆弱性診断ツールの使い方やファイアウォール設定の知識を実践的に学ぶことで、試験の問題にも応用できる視点を身につけました。また身の回りでセキュリティーに詳しいAさんという人がいて、その人の日々の業務を観察することの多かった私は「Aさんだったらどう考えるかな」という観点でセキュリティーの問題を解くこともしばしばありました。
- セミナーや動画の活用 試験対策のセミナーを受講したり、情報処理技術者試験に取り組む動画を見ることで、知識を高めました。どうしても合格したかったのでYouTubeの無料動画だけでなく、有償の動画を見ることもありました。
合格のポイント
合格のために特に重要だと感じたのは、次の3点です:
- 計画的な学習スケジュールの構築 仕事の合間に勉強する時間を確保するため、1日あたりの勉強時間を明確に決め、優先順位をつけて取り組みました。
- 弱点の克服に集中 午後問題のシナリオ形式や長文読解が苦手だったため、問題文を速く正確に読む訓練を繰り返しました。また、暗記に頼るだけでなく、理解を重視して学習を進めました。
- 試験本番への慣れ 模擬試験を活用して本番さながらの環境を再現し、時間配分や緊張感への対応を練習しました。
次へのステップ
情報処理安全確保支援士に合格したことで、自分のキャリアの幅が広がったと感じています。今後はこの資格を活かして、セキュリティ分野のプロジェクトに積極的に関わり、実務経験を積んでいきたいと思います。また、セキュリティと他のIT分野を組み合わせた新しいソリューションの開発にも挑戦していきたいです。
資格取得はゴールではなく、スタート地点に過ぎません。これからも学び続け、実務での活用を通じてさらなる成長を目指していきます。

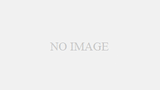
コメント